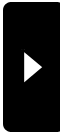2021年06月30日10:14
おみくじについて≫
カテゴリー │知識
皆さんこんにちは!
コロナとの闘い?が長期戦となっている中、毎日ストレスを抱えながら生活されていることではないでしょうか?
そんな中、少しでもほっとして頂けたらと思い、今回はおみくじについて少し触れたいと思います。

おそらく誰もが一度は引いたことがある(引かなくても目にしたことがある)馴染みの深いおみくじですが、実は意外と奥が深いのです。
おみくじについて書かれた本「ニッポンのおみくじ 鏑木麻矢著」から少し紹介したいと思います。

そもそも、おみくじとは何か?
『神々の声を手軽に受け取れるメッセージツール』
『偶然を利用するという原始的な原理で、最もシンプルな形』
『感覚を研ぎ澄ませて自分の力で自分だけのためのお告げを引き出すという、占いの本質にも触れられる』
『中国風の漢詩と、日本の和歌、遊び心の辻占(つじうら)。
三つの要素が、ゆるやかに混ざりつつ共存する。
これが日本のおみくじの特徴である』
う~ん、たかがおみくじ、されどおみくじですね!
おみくじは神社・仏閣の他に、お土産物店で売られていたり、自動販売機やガチャまであり、様々なところで手に入れられるようです。
そんなおみくじですが、いつ頃から登場したのでしょうか?
ルーツを探ってみましょう~!
『お寺に多い漢詩おみくじの定番は、元三大師百籤(がんさんだいしひゃくせん)と呼ばれる。これは天竺霊籤(てんじくれいせん)という中国のおみくじが元になっていて、いつごろ日本に伝わったかは定かではない(でも、伝説はあるようです)』
『古代、シャーマン(巫者ふしゃ)に神々のお告げを和歌で語らせたのが、歌占の始まりである。神社の多くはお寺と一体で、おみくじも漢詩を使っていた。ところが、幕末の尊王攘夷思想から明治の神仏分離令という時代の流れで、神社には日本独自のおみくじをいう機運が高まる。そこで採用されたのが、和歌おみくじ』
『二つの道路が交差しているところを辻という。人々が行き交い、異界と接する場所とされた。その辻に立ち、人々の会話からインスピレーションを得る占いが、古代から行われた本来の意味の辻占。これが江戸末期ごろには紙のくじ形式に姿を変え、、、、洒落た進化をとげる。お菓子の中に入れた形態が現代にも残っている』
そんな訳で、お寺では漢詩、神社では和歌を使ったおみくじが主流となっているようです。
気になるおみくじの吉や凶の順番はどうなっているのでしょうか?
『吉凶の順は基本的に2パターン』
Aパターン:大吉>吉>中吉>小吉>末吉>凶>大凶
Bパターン:大吉>中吉>小吉>吉>末吉>凶>大凶
では、吉凶の割合はどうなっているのでしょうか?
『神社仏閣によって違う』
『一般的な漢詩おみくじ(元三大師百籤)の割合
大吉 17%
吉 35%
凶 30%
その他の吉 18%
割合は多少前後する。
神社仏閣によっては凶を入れていないところもある』
凶は3割も入っているんですね!
私は若いころ京都の三千院で凶を引いたことがありました
リベンジしようと思い、20年後に再び三千院を訪れたのですが、そこでまたまた凶を引いてしまったのです、、、実に100%の確率です!(涙)

おみくじを引く時のマナーもあるようです。
『神社やお寺で引くならば、最初に必ずすべきことがある。
それはズバリ、参拝。
手水舎があるならお清めしてから参拝するのが望ましい』
そして占いをより効果的にするためには?
『①占いたいことを具体的にする
②生年月日と質問を念じる
③精神統一をして無心に引く
④吉凶よりも解説を読み解く』
なかなか奥が深いですね!
でも本の中にも書かれていますが、真剣に引くもよし!楽しく引くもよし!
要は、その人次第ということでしょう~
さて、おみくじを引いたあと、皆さんはどうしていますか?
持ち帰っていいのか?結んだ方がいいのか?決まりはあるのでしょうか?
『よく言われるのは、吉なら持ち帰れ、今日なら結べだが、これも決まりは
ない。自分の好みで決めてよい』
『不要になった場合、捨てるのはよくない。
近所の神社に持っていき、所定の場所に結ぶか、古札納め処などから御焚き上げに出そう』
『すぐに結んでもよい。ただし、木に結ぶのはマナー違反。必ず寺社指定の場所へ』
いかがだったでしょうか?
もっとおみくじについて知りたい方は、是非「ニッポンのおみくじ」をご一読下さい
コロナ感染が終息して、自由に外出や旅行ができる日が早く訪れるといいですね!
そんな日が来たら、私はもう一度三千院に行って、三度目のおみくじを引いてみようと思っています
コロナとの闘い?が長期戦となっている中、毎日ストレスを抱えながら生活されていることではないでしょうか?
そんな中、少しでもほっとして頂けたらと思い、今回はおみくじについて少し触れたいと思います。

おそらく誰もが一度は引いたことがある(引かなくても目にしたことがある)馴染みの深いおみくじですが、実は意外と奥が深いのです。
おみくじについて書かれた本「ニッポンのおみくじ 鏑木麻矢著」から少し紹介したいと思います。
そもそも、おみくじとは何か?
『神々の声を手軽に受け取れるメッセージツール』
『偶然を利用するという原始的な原理で、最もシンプルな形』
『感覚を研ぎ澄ませて自分の力で自分だけのためのお告げを引き出すという、占いの本質にも触れられる』
『中国風の漢詩と、日本の和歌、遊び心の辻占(つじうら)。
三つの要素が、ゆるやかに混ざりつつ共存する。
これが日本のおみくじの特徴である』
う~ん、たかがおみくじ、されどおみくじですね!
おみくじは神社・仏閣の他に、お土産物店で売られていたり、自動販売機やガチャまであり、様々なところで手に入れられるようです。
そんなおみくじですが、いつ頃から登場したのでしょうか?
ルーツを探ってみましょう~!
『お寺に多い漢詩おみくじの定番は、元三大師百籤(がんさんだいしひゃくせん)と呼ばれる。これは天竺霊籤(てんじくれいせん)という中国のおみくじが元になっていて、いつごろ日本に伝わったかは定かではない(でも、伝説はあるようです)』
『古代、シャーマン(巫者ふしゃ)に神々のお告げを和歌で語らせたのが、歌占の始まりである。神社の多くはお寺と一体で、おみくじも漢詩を使っていた。ところが、幕末の尊王攘夷思想から明治の神仏分離令という時代の流れで、神社には日本独自のおみくじをいう機運が高まる。そこで採用されたのが、和歌おみくじ』
『二つの道路が交差しているところを辻という。人々が行き交い、異界と接する場所とされた。その辻に立ち、人々の会話からインスピレーションを得る占いが、古代から行われた本来の意味の辻占。これが江戸末期ごろには紙のくじ形式に姿を変え、、、、洒落た進化をとげる。お菓子の中に入れた形態が現代にも残っている』
そんな訳で、お寺では漢詩、神社では和歌を使ったおみくじが主流となっているようです。
気になるおみくじの吉や凶の順番はどうなっているのでしょうか?
『吉凶の順は基本的に2パターン』
Aパターン:大吉>吉>中吉>小吉>末吉>凶>大凶
Bパターン:大吉>中吉>小吉>吉>末吉>凶>大凶
では、吉凶の割合はどうなっているのでしょうか?
『神社仏閣によって違う』
『一般的な漢詩おみくじ(元三大師百籤)の割合
大吉 17%
吉 35%
凶 30%
その他の吉 18%
割合は多少前後する。
神社仏閣によっては凶を入れていないところもある』
凶は3割も入っているんですね!
私は若いころ京都の三千院で凶を引いたことがありました

リベンジしようと思い、20年後に再び三千院を訪れたのですが、そこでまたまた凶を引いてしまったのです、、、実に100%の確率です!(涙)

おみくじを引く時のマナーもあるようです。
『神社やお寺で引くならば、最初に必ずすべきことがある。
それはズバリ、参拝。
手水舎があるならお清めしてから参拝するのが望ましい』
そして占いをより効果的にするためには?
『①占いたいことを具体的にする
②生年月日と質問を念じる
③精神統一をして無心に引く
④吉凶よりも解説を読み解く』
なかなか奥が深いですね!
でも本の中にも書かれていますが、真剣に引くもよし!楽しく引くもよし!
要は、その人次第ということでしょう~
さて、おみくじを引いたあと、皆さんはどうしていますか?
持ち帰っていいのか?結んだ方がいいのか?決まりはあるのでしょうか?
『よく言われるのは、吉なら持ち帰れ、今日なら結べだが、これも決まりは
ない。自分の好みで決めてよい』
『不要になった場合、捨てるのはよくない。
近所の神社に持っていき、所定の場所に結ぶか、古札納め処などから御焚き上げに出そう』
『すぐに結んでもよい。ただし、木に結ぶのはマナー違反。必ず寺社指定の場所へ』
いかがだったでしょうか?
もっとおみくじについて知りたい方は、是非「ニッポンのおみくじ」をご一読下さい
コロナ感染が終息して、自由に外出や旅行ができる日が早く訪れるといいですね!
そんな日が来たら、私はもう一度三千院に行って、三度目のおみくじを引いてみようと思っています